coffee &
paperbacks
coffee & paperbacks は、同じ小説を読んできてあれこれおしゃべりをする、誰でも参加歓迎ののんびりとした読書会です。
あらすじ
主人公は倉島泉。彼女の伝記を執筆しようとするライターが、関係者に取材し、彼女がどんな人生を送ったのかを描く、という形をとって物語は進む。
諏訪にある旅館「たから」の長女として生まれた泉。生後まもなくして祖父母をなくし、母には「なんだか不吉な子だわ。父さんと母さんの生き血を吸って生れてきたみたいに」疎まれ、病弱だが美しく賢い妹が溺愛される影で、ほとんどネグレクトといっていいような露骨に冷たい扱いを受けて育つ。
やがて大きくなり家業を継ぐと、左前だった旅館を、時代に先駆けて健康志向と安全な食の宿として改革する大胆なプランを打ち出し、抜群の経営センスを発揮するが、女将であるのに表にたたずサポート役に徹し、周りからは農園のお手伝いさんとみられもする。
女であることを止めた醜い女などと周囲に馬鹿にされても意に介することもなく、何もほしがらず、結婚相手が若い女中・奈美と恋仲になり離婚を持ちかけられても、あっさりと応じ、財産にも一切頓着しない。そんな純粋の無私を貫く泉に、周囲は不気味さすら覚える。
あるきっかけで彼女を身辺調査することになった元ヤクザの小口だけが、泉が何を生き甲斐とし、何を喜びとしているのかを理解するのだが…。
about the author
姫野 カオルコ
1958年滋賀県生まれの女性作家。2010年発表の本書を含め、何度も直木賞の候補に名を連ねる。著書多数。1997年『受難』、2003年『ツ、イ、ラ、ク』、2006年『ハルカ・エイティ』、2010年『リアル・シンデレラ』によって直木賞にノミネートされた実力派。
from the facilitator
本がとても好きな友人に貸していただいた本を、この機会に読んでみたいと思って。前2回の本とはまた違って、(たぶん)ストレートな物語作品なので、じっくり筋にひたってみんなで語りたいと思います。
読書会を終えて

ドーナツの中心
「主人公が目立たないじゃないか」(単行本11ページ)
というライターのことばで開幕するこの物語ですが、本当にそう? という問いかけから読書会はスタート。
シンデレラってけっこう目立つよ、という声が多かったのですが、一方でシンデレラ自体の描写や記述は少ない、との指摘も。
その意味で、シンデレラはドーナッツの穴のような「負の中心」、からっぽの中心であり、それ自体は空虚な存在かもしれません。
この物語の主人公・泉も、自身がはっきりと特徴づけられるというよりは、証言するひとによって評価がまったく違う存在として描かれています。その意味で、負の中心として機能しているといえます。
「あれが女の人だと思うのよ……ああいうものでしょう? 男の人だってそう……。みなそれなりにおしゃれして……(…)
お隣の部屋の今の彼女みたいに二十代前半なら、髪のほんの撥ね具合だとか、分け具合だとかを細かく気にして、お給料の大半を洋服や靴なんかに注ぎ込んで……、いつか白馬に乗った王子様に会えるかもと期待しつつも、毎日毎日はたいてい平凡で、それでもどこかでドキドキしてる……それがふつうの女の人じゃないの?」(文庫328ページ/単行本319ページ)
この引用は、「ところが泉はそういうふうではまったくない。そんなのおかしい」というネガティヴな評価です。
一方で、元ヤクザとして都会の存在といえる小口の感想はまったく違います。
「侘しそうだとか、悲しそうだとかいうふうには見えなかった。見てくれからして垢抜けれるじゃないか」
「えっ。垢抜けてる? どこが?」
「だって、そうだろ」(単行本326ページ)
このように、泉の外見の評価が、ひとによって醜い/美人と真逆に表現されるのが不思議でまた面白いところですが、東京の男性あるいは都会の男性は泉を美人と評し、地元のひとたちはそう思わない、となっているのではないか、という意見が出ました。
地元では野良着で土まみれになって埋没している女性が、都会人の目から見れば健康的で美しい、ということはあり得るかもしれません。
それは、妹・深芳を検討してみるとはっきりしてきます。
「醜いあひるの子」として描かれる泉に対して、妹は生来の愛嬌を持った存在として描かれています。
ミーちゃんを誰かが褒めると、深芳は柾吉の胸にきゅうっと顔を埋めてから、そうっと上目で相手を見た。そのしぐさがまたかわいらしく、人は深芳を褒める。(文庫33ページ/単行本31ページ)
こういう子いるよね、という声がでました。器用にたちまわり、器量もよく、地元の華としてちやほやされて育つ子。
ところが、物語後半、駆け落ちし東京に出て行ったあとの深芳は、スナックを経営し地元の代議士の愛人に収まるという具合に、なんだか凡庸な存在になって都会に埋没してしまいます。物語にもほとんど登場しなくなります。
地元のアイドルは、都会では「どこにでもいる女」にすぎないのかもしれません。

泉と母親
前半では、子供時代の泉が虐待に近い待遇を受けて育つさまが語られています。
「泉はいつも、あんたはお姉さんなんだからと、母ちゃんからきつく言われてますんじゃ。たまには妹役をさせてやって下さらんか。今日は泉の誕生日なんで」(単行本47ページ)
母親にネグレクトされて育つ泉の唯一の味方である叔父も、すぐに亡くしてしまいます。
なぜ母・登代が鬼子のような扱いをするのかについては、ゆきずりの男との間にできた子ではないかと心配しているからだと読めますが、そのところは、はっきりとは書かれていません。
しかし、「浅知恵の小悪魔」とライターに評される登代の性格は、非常に分裂的で、その行動や思いは前意識的だという指摘がありました。
彼の声、話し方を、今日の五時より前には魅力に感じていた。今はぞっとする。細面の、目鼻だちのはっきりした、ハンチング帽をかぶると鍔の影で知的な憂いさえただよわせて見えるその顔は、たしかに今でも美男子だが、もう見るのもいやだ。彼が使った枕も汚く見える。何もかもが登代の心をぎざぎざに引っ掻く。(文庫232ページ/単行本226ページ)
魅力的に映ったゆきずりの男が、野卑な言葉を発した瞬間、たちまち嫌悪の対象となる。こういう心理の動きは不自然ではないかもしれません。しかし一方で、登代の一貫性のなさ、心持ちのころころ変わる性格を表しています。
「……でも丈夫な子だったわ。多少のことじゃビクともしないっていうか、感じないっていうか、たくましいっていうか。えっ、だれがそんなこと言ったの? いいえ全然……。全然、そんなことはないわ。泉とわたしはとても仲がよかったわよ。初めての子だったから過保護にしちゃって……。仲がよかったわよ……」(文庫236ページ/単行本229ページ)
泉との関係についてこう語る場面も、必ずしも「嘘」を言っているわけではない、その場面場面で本気で言っているという意見に、多くのひとが頷きました。

無私の聖者
愛嬌や愛想をふんだんに備えた妹・深芳に引き換え、泉はまったく飾らない天然そのものです。
水道でじゃぶじゃぶと顔を洗う。洗って、作務衣のたもとから手拭いを出して拭いた。
「相変わらずね、泉ちゃんは」
自身を拡大しようとも縮小しようともつゆにも発想しないところが、である。この冷静な女王である華子が泉を贔屓にしたのは、泉が常にその身の丈のままでいるところだった。それは素直ということである。(文庫135ページ/単行本131ページ)
地元の名家の奥さんはこうした泉の飾らなさを好ましく思い縁談をもちかけようとするのですが、ほとんどのひとは理解できず邪推したり馬鹿にして遠ざけたりします。
「だって、あまりに泉さんじゃない人にばかり都合がよすぎるじゃないですか……」
泉が怖かった。睫毛に涙をためて奈美は告白した。(文庫263ページ/単行本255ページ)
離婚の話し合いになっても、いっさいに頓着せず周りに良よかれと配慮し、どこまでも無私を貫く泉に、かえって周囲は不気味ささえ感じ、よけいな気を回して「自滅」(は言い過ぎかもしれませんが、すくなくとも「大騒ぎ」)していきます。
まわりは愚かなふつうの「俗人」であり、それに対して泉は「聖者」的、宗教者や修行者のようです。
次のくだりは、そんな聖者と俗人の関係を語っているところとして読めますが、多くのひとがひっかかりを感じて抜き出した箇所です。
さらさらと軽快に物語が流れていくこの小説は、ところどころ、突然ぐっと心理学的な深みをます箇所がいくつかあります。
愛されて育った者は、他人の、一抹の気遣いにさえ敏感に気づく才能が培われる。
愛されて育たなかった者は、愛されて育った者を頭ごなしに妬み怒ることが多い。だがまれに、愛されて育った者の才能を、遠くから憧憬する者がいる。その憧憬は、たとえばバイエルを経てツェルニーを履修した子や五〇メートル泳げる子への瞠目に似た、心と肉体がきわめて一致した、具象的で身近な、小学生のような敬いである。 だから、『「他人の自己に対する気遣いに敏感に気づく才能」への敬い』は、換言すれば、さびしい才能である。
しかし、愛されて育った者には、その才能が怖い。当然といえば当然である。愛されて育った者には、さびしさに対する鈍感さは、斬っても殴っても倒れない強靭さに映るからである。映ってしまうからである。(文庫249ページ/単行本242ページ)
泉を理解できず不気味がる周囲の人間の中にあって、一人酒の楽しみを知る小口だけが、泉の気持ちを理解することができます。
自分で自分にしゃべっているのでなければ、だれかもう一人と、煮込むように会話をしたい。鶏の骨が溶けるように論理が酒でとろとろになり、翌日には忘れてしまうような会話の煮込みを肴にして飲むのである。(文庫339ページ/単行本330ページ)
小口は笑った、つられたのだ。サラダを口に入れた泉の、えへへといういかにもうれしそうな夷顔に。(文庫341ページ/単行本331ページ)
お独りさまを満喫する泉の姿を、小口は自分と重ね合わせています。
小さな小さな、取るに足らないほど小さな温かいことが、一日のうちに一つか二つ、よくできた日なら三つか四つほどおこり、夜が来てその日が終わり、次の日になってまた、一つか二つおこり、次の次の日になって、一週間がたち、一年が過ぎ、ひとは暮らしていく。それが何にも勝る幸福であることを、少量をきれいに飲みさえすれば、酒は思い出させてくれる。(文庫359ページ/単行本349ページ)
この物語に登場する他のひとたちは、こうした「小さな」喜びを理解することができません。
かつて「吸血鬼」のような暮らしをしていた元ヤクザの小口だけが理解できます。そもそも「小口」という名前からして、「小さな幸せ」性を付与されているという指摘がありました。
空き瓶をまとめたり、壊れたストーブを積んだりしていると、生き返ったような喜びがあったと小口は言う。(単行本334ページ)
ぽちゃぽちゃした隣人は自分が若いということをよく知っていた。若さは男を惹きつけられると。だから黄味がかっていた。だからそそった。女がかわいいとは、白色ではなく、黄味がかっていることであると小口は言う。(単行本335ページ)
この「黄味ががって」は、卵を連想させる比喩と読めそうですが、健全な性欲もあって、アパートの隣人とやがて恋仲に入っていきますが、一方で、泉に惹かれてもいます。
ラストの場面、泉の小屋で手をつないで眠るところは、泉の唯一のラブシーンといえるかもしれません。
しかし、そのシーンは、現実なのか小口の夢なのか判然としない形で描かれています。
子供の頃はふつうの子供としてネグレクトに苦しんでいた泉は、いつから無私を貫く聖性を獲得するのでしょうか。
ここが、この物語の重要な点であり、また、もう一歩うまく描ききれていないところではないか、という議論が続きました。
非常にグラマーで、都会の男性には「すごい美人」として描かれ、食べ物や感覚的な喜びを知っていて、宿の客のニーズをはっきりつかめる他者への深い想像力をもっているのに、性的なことがらにはまるで興味を示さない泉の造型にしても、ちょっと「ありえないんじゃないか」という違和感を拭えない男性もいました。別の場所、たとえば東京で泉が暮らしたらきちんと充実した性生活を持っていたのではないか、と反論したのは女性の参加者でした。
3次会まで続いたアフタートークでは、見方によって美醜の境界を行き来する泉のモデルは小池栄子がかなり近いのではという意見に皆うなずきました。綾瀬はるかは? という声には賛否半々。
また、ある参加者は、美醜の感じ方は思ったよりもずっと文脈依存的だということを、マレーシアでは美女と感じた女性が日本に帰国してみるとそうでもなく思えたという体験から話してくれました。
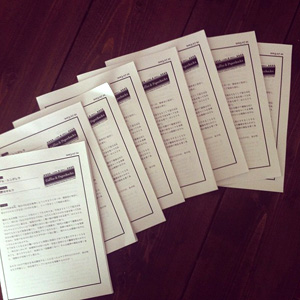
Today's coffee & tea

【コーヒー】
TERA COFFEE and ROASTER 「さわやかブレンド」
【紅茶】
TEAPOND 「ダージリン タルザム農園」「ポーラーミント」「プリンセス ライチ」
